こんにちは、BiKaoです。
仕事でMBSEの布教をしていますが、最新の情報を調べるのも大変なので、AI(ChatGPT)に調べてもらいました。こういう情報はGrokのほうが得意らしいのですが、今回はChatGPTに調べてもらいました。
AIに相談したこと&返ってきたアドバイス
Q.2025年5~6月のMBSE最新情報を調べて教えて
A.
- SysML V2が正式リリース
- 産業分野ごとにMBSE活用が本格化
- MBSE×AI活用・研究が進展
- 教育・人材育成に大きな投資
- オープンソースと学術研究の発展
- 主な国際会議・イベントで議論加速
まとめ:
2025年初夏は「MBSE実践フェーズ」への移行期。
SysML v2・デジタルスレッド・AI活用・教育投資の4本柱が、世界中の産業界で一気に加速しています。
とのことです。そこまで外れてはいなさそうですが、最新というよりはここ数年のって感じがしますね。
まとめ
AIに相談することで、MBSEの最新情報について収集することができました。
自分でいろいろ調べるのは大変ですが、概要であればAIに手伝ってもらうというのもありかもしれません。
一番いいのは自分で毎日少しずつ調べたりするのがいいとは思いますが、続けるのは大変ですからね。
これからも「AI×生活」のテーマで、自分なりにいろいろ発信していきたいです。
実際のやり取り
質問
2025年5~6月のMBSE最新情報を調べて教えて
回答
MBSE(モデルベースシステムズエンジニアリング)の最新情報について調査しますが、もう少し具体的に教えていただけますか?以下の点を教えていただけると、より的確な調査ができます。
- 関心のある分野(例:航空宇宙、自動車、ソフトウェア開発、学術研究など)
- 求めている情報の種類(例:最新のツールやソフトウェア、業界動向、学会・カンファレンスの発表、企業の取り組みなど)
- 情報の言語(日本語中心か英語も含めてよいか)
ご希望の範囲を教えていただけますか?
質問
すべて
回答
了解しました。2025年5~6月におけるMBSE(モデルベースシステムズエンジニアリング)に関する最新情報を幅広く調査します。対象はすべての分野(航空宇宙、自動車、ソフトウェアなど)およびあらゆる情報タイプ(ツール、業界動向、カンファレンス発表、企業の導入事例など)とし、日本語・英語を問わず参照します。
調査が完了しましたら、わかりやすく整理してご報告します。
MBSE最新情報(2025年5月~6月)
産業別のMBSE動向
航空宇宙分野: 航空宇宙業界では、MBSEが製品開発効率向上の鍵として位置付けられています。欧州宇宙機関(ESA)は「Agenda 2025」で、従来の文書駆動型開発をMBSE中心に刷新し、宇宙機の開発期間30%短縮・コスト桁違い削減を目指すと明言しました。NASAでも、有人月飛行計画「アルテミス」でオリオン宇宙船の電気系統をMBSEに基づくデジタルツインとして構築し、従来以上のシステム把握とリアルタイムシミュレーションを実現しています。日本の宇宙航空研究開発機構(JAXA)でも概念設計段階からMBSE手法(OpenCAESAR手法など)の適用を進めており、厳密さと開発スピードの両立に取り組んでいます。大手メーカーでは、ボーイングがT-7A練習機のデジタル開発などでMBSEを先行活用した実績を持ち、現在は将来の人材育成も含めてMBSE推進に注力しています(後述の教育連携参照)。三菱重工業のような日本企業も、社内の航空機・宇宙部門でMBSEを全社横断プロセスに統合する戦略を掲げ、商用航空機やロケット開発で要求やアーキテクチャのオントロジーモデリングと解析連携を図っています。
防衛分野: 国防領域でもMBSEはデジタル変革の中核です。米国防総省(DoD)はデジタルエンジニアリングを全調達ライフサイクルに組み込む方針(DoD指令5000.97)を打ち出し、迅速かつ統合的な能力提供の手段としてMBSE活用を重視しています。2025年6月開催の「Digital Engineering for Defense Summit」では、Air Forceの調達加速やモデルベースのテスト&評価改革、スピードと精度を両立した戦力提供といったテーマで、デジタルエンジニアリング施策の展開とMBSEの貢献が議論される予定です。実際、米空軍や海軍では複雑兵器システムの開発にMBSEを導入し、要求から設計・試験までのトレーサビリティ確保や設計変更の迅速化に効果を上げています。また、信頼性の高いモデルの構築も重視され、モデルの検証や標準化(例:軍用航空規格ARP4754との整合)を通じてMBSEを兵器システム開発プロセスに定着させる動きがあります。国防系企業や軍研究所もMBSEとAIの融合(後述)による意思決定支援など先端的な取り組みを進めており、MBSEは防衛分野のデジタルトランスフォーメーションに不可欠な位置づけとなっています。
自動車分野: 自動車業界でも、電動化・自動運転など車両の高機能化に伴いMBSEの重要性が増しています。ソフトウェア定義車両への移行で電子電気アーキテクチャが高度化する中、要件から各サブシステム(電子制御ユニット、センサー、ソフトウェア)まで一貫したモデルで管理する手法としてMBSEが活用されています。例えばトヨタ自動車では、グループ会社の「Woven by Toyota」が複数チーム間でのMBSEデータ管理とセキュリティの課題に取り組んでいることを2025年3月のイベントで報告しており、大規模開発組織でのモデル共有・統制がテーマになっています。同イベントではトヨタ本社からMBSE推進に伴うモデラー人材育成の事例も紹介され、社内教育を強化しモデリングスキルを底上げしている状況が示されました。また、自動車業界全体での知見共有も活発で、INCOSE日本支部は2024年に自動車WGを設立し、2025年3月に自動車と航空のSE専門家によるパネル討論を開催するなど、業界横断でMBSEのベストプラクティスを模索しています。欧米の自動車メーカー(GM、フォード、BMW等)もモデルベース開発手法をシステムレベルに拡張しており、要求管理や機能安全規格(ISO 26262)への適合をモデルで検証・保証する流れが一般化しつつあります。特に機能の再利用や製品ラインエンジニアリングの文脈でMBSEの価値が認識されており、「MBSEの真価は将来、モデル資産の再利用と製品ライン管理において発揮されるだろう」という分析もあります。
ソフトウェア/IT分野: ソフトウェア業界そのものでも、複雑なクラウドシステムや企業ITシステムの設計管理にMBSE的手法を適用する動きがあります。MBSEは本来ハードウェア・ソフトウェア含むシステム全体を対象としますが、昨今はソフトウェアアーキテクチャのモデル化や、システムモデルとコードの往復可能な開発(モデル駆動工学)にも注目が集まっています。例えばOMGにより策定されたSysML v2 APIを用いて、システムモデルと各種ドメインツール(ソフトウェア設計ツール等)の双方向連携を容易にしようという取り組みが進んでいます。NASA/JPLではオープンソースのOpenMBEE v2プロジェクトを主導し、モデルリポジトリにRDFベースの意味情報を持たせて知識推論に活用する試みを行っています。また、組込みソフト分野では、SysMLモデル上で動作ソフトの振る舞いを定義し自動コード生成する道が拓けつつあります。実際、OMGのSysML v2標準にはAADL(航空宇宙向けアーキテクチャ記述言語)のライブラリが追加され、SysML v2モデルから組込みソフトの詳細設計を行い、Rustなど実装コードを生成する実験も報告されています。大手MBSEツールベンダー各社もソフトウェア開発プロセスとの連携機能を強化中で、SiemensやIBMは要求管理・DevOpsツールとの統合を図り、システムとソフトウェアの単一リポジトリ(Single Source of Truth)を実現しようとしています。さらに、MathWorks(MATLAB/Simulink)もMBSEエコシステムに参画し、システムモデルと連動したシミュレーション・解析ソリューションを提供しています。このようにソフトウェア分野では、MBSEを通じてシステム全体の中でソフトウェア設計を捉え、他分野(機械・電気)との調整を行う動きが顕著です。
医療機器・ヘルスケア分野: 医療機器業界でもMBSE採用が進みつつあります。高度化する医療機器(例:手術ロボット、スマートデバイス)では規制遵守(FDA等)や安全解析の厳格さが要求されるため、要求からリスク分析、検証まで一元管理できるMBSEが有用です。INCOSE主催の「医療分野におけるシステムエンジニアリング」カンファレンス(2025年4月, 米ミネアポリス)でも、医療業界でのSE実践向上がテーマとされ、スマート人工関節(スマート義膝)のデジタルスレッド構築による整形外科イノベーション事例などMBSE活用報告がありました。この事例では、人工関節システムの要件・設計・生産・試験データをMBSEモデル上でトレース可能に管理し、関係者間の情報共有と開発サイクル短縮を実現しています。また医療機器メーカー各社は、製品開発プロセスにMBSEを組み込むことで設計文書の整合性確保と設計変更時の影響分析効率化を図っており、一部ではバーチャルプロトタイプによる治験代替の検討も行われています。医療分野特有の課題である多職種連携(医師・工学者・規制当局などの協働)にもMBSEが寄与すると期待され、共通言語としてのモデルを介したコミュニケーション改善の報告も増えています。
MBSE関連ツール・プラットフォームの最新動向
業界のMBSEツールやプラットフォームにも2025年にかけて大きなアップデートが見られます。特に注目すべきトピックは、次世代標準SysML v2への各社対応と、デジタルスレッド実現に向けたツール連携機能の強化です。
- SysML v2標準の確立: モデル記述言語であるSysMLはMBSEの中心技術ですが、2024年末に待望のSysML v2仕様が正式リリースされ、2025年は各種ツールがこの新標準対応を進めています。SysML v2では言語の表現力と精密さが向上し、自動処理(モデル検証・変換)の容易化やAPI経由での他ツール連携が重視されています。INCOSEやOMGではSysML v2普及に向けた移行ガイドも作成中で、IW2025では旧来SysML v1からv2への移行ベストプラクティスが共有されました。今後は企業が自社MBSEプロセスをSysML v2にスムーズに切り替えられるよう、トレーニングやモデル変換ツールの整備が進む見込みです。
- 主要MBSEモデリングツールのSysML v2対応: 大手ベンダー各社はSysML v2対応版ツールの提供を開始しています。Dassault Systèmes(No Magic)のCameo Systems Modeler(旧MagicDraw)は、OMGのSysML v2ベータ仕様策定に深く関与しており、CATIA Magicシリーズとして早期にv2対応を表明しました。IBMは従来のRational Rhapsodyを発展させ、SysML v2対応の新製品Rhapsody SEを投入しています。Ansysも新たにAnsys SAM(Systems Architecture Modeler)というSysML v2対応モデリングツールを発表し、既存のシミュレーション群と接続したシステム設計を提案しています。老舗のSparx Systems Enterprise ArchitectやPTC Modeler(Windchill Modeler)もプラグイン等でv2をサポート予定であり、**2025年はMBSEツール群の“SysML v2元年”**と言える状況です。このようにモデリング環境が一斉にアップデートされることで、ユーザ企業側でも将来を見据えたツール選定やトレーニング計画を練り直す動きが出ています。
- SiemensとIBMの協業による新プラットフォーム: 2025年6月、SiemensとIBMは共同で開発した新しいMBSEクラウドツール「Systems Modeler for SysML v2」を発表しました。これはSiemensの産業DXプラットフォーム「Xcelerator」に組み込まれたWebベースMBSE環境であり、IBMのMBSEエンジン(Rhapsody SE)を核に据えてSysML v2オープン標準に完全準拠しています。特徴は、SiemensのPLMシステム「Teamcenter」とシームレス統合し、システムモデルを機械・電気・ソフト各設計ドメインの詳細設計ツールとデータ連携できる点です。これにより、MBSEモデルを起点としたデジタルスレッド(要求→設計→検証→製造の一貫データ連鎖)が実現し、下流工程への設計伝達や変更影響分析を自動化できます。同ツールは直感的なWebインターフェースで複数部門の協調を促進するとされ、Siemensは「最新のSysML v2標準をサポートすることでエンジニアのクロスドメイン協調と効率化を加速する」と述べています。
- オープンソースMBSEツールの台頭: モデリングツール分野ではオープンソースの動きも活発です。フランスのObeo社はEclipseプロジェクトとしてSysONというWebベースのオープンソースSysML v2モデラーを開発中で、2025年に入り精力的に機能拡充を行っています。最新リリース(SysON 2025.2)では大規模ダイアグラム閲覧用ミニマップや右クリックメニュー追加、エクスプローラ表示のカスタマイズなど使い勝手を向上させる新機能が実装されました。さらにモデルクエリ言語(AQL)の実行機能やダイアグラムのPNGエクスポートも追加され、オープンソースながら実務に耐える充実度を備えつつあります。SysONは視覚的なGUIモデリングに加えてテキストエディタやフォーム入力も可能な柔軟性を持ち、軽量でカスタマイズ可能なSysML v2ツールとして注目されています。また、NASA有志らによるOpenMBEE(オープンソースのモデルリポジトリ/ビュー生成フレームワーク)もSysML v2対応の「OpenMBEE 2」構想が進行中で、モデルをWeb上で閲覧・ドキュメント化したりRDF形式で外部システムと連携する次世代リポジトリを目指しています。オープンソースの台頭により、学術機関や中小企業でも低コストで最新MBSEに触れられる環境が広がりつつあります。
- ツール間連携とデジタルスレッド: 2025年はツールエコシステムの統合も大きなキーワードです。MBSE単体ではなく、PLM(製品ライフサイクル管理)やシミュレーション、要件管理ツール等との連携によるデジタルスレッド構築が各社から提案されています。前述のSiemens-IBMソリューション以外にも、Intercax社のSyndeiaはSysMLモデルと各種エンジニアリングデータベース(要求管理やCAD、シミュレーション)を双方向リンクするミドルウェアを提供し、2025年版ではAIを用いた自動マッピング機能を強化しています。SodiusWillert社のSECollabも2025年に初公開されたWebコラボレーション基盤で、SysML v2モデルと他のライフサイクルツール間のトレーサビリティを構築できます。これら統合ツールにより、要求やテストケース、CAD図面などをMBSEモデルと紐付けて管理し、関係者が常に最新情報にアクセスできる「単一の真実源(Single Source of Truth)」環境が整いつつあります。またMathWorks(MATLAB/Simulink)も他ツールとの接続インターフェースを拡充し、SimulinkモデルとSysMLモデル間でデータ交換や整合チェックを行うソリューションを提供しています。総じて、2025年前半は**「MBSEツール群の相互運用性」**が飛躍的に高まった時期であり、ユーザー企業は様々なベンダーソリューションを組み合わせて自社エンジニアリングIT基盤を統合し始めています。
主な学会・カンファレンスでのトピックとトレンド
2025年5~6月にかけて、MBSEに関する多数の国際会議・業界イベントが開催され、最新トレンドが議論されています。以下に主なイベントとそこでの注目ポイントを整理します。
- INCOSE International Workshop 2025(2月・セビリア): システムエンジニアリング国際評議会(INCOSE)の年次ワークショップでは、SysML v2への移行が最大のテーマとなりました。IW2025ではMBSE作業部会によるチュートリアルや事例発表が相次ぎ、特に17社が参加したSysML v2ベンダーショーケースでは各社の対応状況が示されました。分類すると、Dassault(Cameo)、IBM(Rhapsody SE)、Ansys(SAM)、Sparx EA、Obeo(SysON)、PTC(Modeler)、Sensmetry(SysIDE)等のモデリングツール各社、IntercaxやSodiusWillert等のデジタルスレッド統合ツール、IncQueryやMathWorks等のモデル解析・可視化ソリューションがそれぞれSysML v2対応のデモを行っています。特にオープンソース勢(Obeo SysONやOpenMBEE v2プロジェクト)の存在感もあり、MBSEコミュニティ全体で新言語標準普及に取り組む熱気が伝わりました。併せて、Lockheed MartinやSAICの有志が進める**「SysML v2移行ガイドライン策定WG」から、組織的にv1からv2へ乗り換える際の勘所が共有され、ツール面だけでなく手法面の準備も進んでいます。またIWではJPLのEd Seidewitz氏からOpenMBEE v2**構想(モデルリポジトリの次世代化とセマンティックWeb技術の活用)が紹介されるなど、学術・オープンコミュニティ発の新展開も注目を集めました。
- INCOSE International Symposium 2025(7月・オタワ): INCOSEの年次国際シンポジウム(IS2025)は7月下旬に予定されており、MBSEが引き続き大きなテーマとなる見通しです。スポンサー企業のIntercax社は本イベントでデジタルスレッド技術(Syndeia 3.6)の最新動向を披露予定であり、他のMBSEツールベンダーや産業界の発表も予想されます。ISでは例年、各国の先進事例やパネルディスカッションを通じて産業分野別のMBSE成熟度や人材育成が議論されるため、2025年時点での世界的なMBSEトレンドを総括する場となるでしょう。特にSysML v2標準が正式公開後初のISであるため、ユーザー企業の実導入報告や標準化団体からの最新報告(OMGの進捗など)がハイライトになると見られます。
- MBSE Summit 2025(6月2~3日・オーストリアTraunkirchen): 欧州MBSEコミュニティの有志が主催する本サミットは今年で4回目を迎え、「Ready to board」のテーマで開催されました。広告抜きの少人数カンファレンスながら内容は濃く、ドイツ航空宇宙センター(DLR)による「マルチディシプリン宇宙システム設計のデータ駆動化」や、OMG MBSE共同体共同議長でSysML提唱者でもあるSanford Friedenthal氏による**「SysML v2時代のMBSE手法の進展」**などの基調講演が行われました。またスウェーデンSaab社からはグリペン戦闘機開発へのMBSE適用とその価値に関する講演があり、軍用航空機開発におけるMBSE効果が具体的に共有されています。Siemens社の講演では「MBSE導入を成功させるための組織変革」(システムズエンジニアリング部門リードによる発表)もあり、ツールや理論だけでなく現場での実践ノウハウに焦点が当てられました。さらに複数のワーキンググループに分かれて参加者同士の討議も行われ、その成果はレポートとして公開される予定です。参加者からは「業界と学術の信頼関係に基づく議論ができた」との声もあり、欧州におけるMBSEの熱量とコミュニティの広がりを感じさせるイベントとなりました。
- INCOSE India MBSE Summit 2025(6月13~14日・インド Pune): インドINCOSEチャプター主催による大規模イベントで、インド国内外から200名以上が参加しました。テーマは特定されていませんが、宇宙・防衛、自動車、製造、ヘルスケア、学術といった幅広いセクターから発表者が集い、インドにおけるMBSE適用事例や課題が議論された模様です。インドは宇宙(ISROの探査計画など)や国産軍用機開発でMBSEを国家的に推進しており、産学官の連携も盛んです。本サミットでも政府系プロジェクトの紹介やパネル討論が行われ、MBSEが新興国におけるシステム開発高度化の鍵として期待されていることを示しました。Intercax社など国外企業もスポンサー参加しており、グローバル企業もインド市場でのMBSE拡大を視野に入れている様子がうかがえます。
- INCOSE Systems Engineering in Healthcare Conference 2025(4月29日~5月1日・米国ミネソタ州): 医療分野に特化したSEカンファレンスで、テーマは「ヘルスケア産業におけるSE実践の推進」でした。MBSEも主要トピックの一つとして取り上げられ、Intercax社は**「スマート人工膝関節におけるデジタルスレッド – 整形外科イノベーションの推進」**と題した事例発表を行いました。これは次世代医療機器(スマート義足・インプラント)開発にMBSEとデジタルツインを適用したもので、製品ライフサイクル全体のデータを一元管理しつつAI解析で知見を引き出すアプローチが紹介されました。ヘルスケア分野では他にも、システム思考を医療プロセス改善に応用したケーススタディや、医療機器メーカー各社のMBSE導入状況の共有があり、参加者は安全規制対応や臨床ニーズの変化に柔軟に対応できる開発プロセスとしてMBSEの可能性を議論しました。医療はSE後発分野ですが、本会議の成功はMBSEが医療産業でも本格的に展開期に入ったことを示唆しています。
- MBSE Cyber Systems Symposium 2025(4月7~10日・米国リノ): Dassault Systèmes(No Magic)がスポンサーとなり開催されたイベントで、サイバーセキュリティとMBSEの交点に焦点を当てたものです。ここではモデルとセキュリティ解析の連携や軍事サイバー物理システムへのMBSE適用などが議題に上り、欧米の防衛産業関係者・研究者が集まりました。Syndeia 3.6の最新機能デモや、DassaultのMagic Gridフレームワークを使ったセキュアなシステム設計手法のワークショップも行われ、参加者は実践的な知識を深めました。MBSEツール各社もブース出展し、モデル上で脅威分析やリスクアセスメントを行う統合ソリューションを紹介しています。サイバーセキュリティ分野ではモデルに基づく形式手法との親和性も高いため、MBSEを軸にした今後の研究開発が期待されます。
- 2025 MBSE Symposium (NDIA Tennessee Valley Chapter)(5月21~22日・米国ハンツビル): 全米防衛工業協会(NDIA)テネシー支部とINCOSE他の共催によるMBSEシンポジウムで、テーマは「デジタルエンタープライズへの変革」でした。国防・宇宙・航空セクターのリーダーや専門家が一堂に会し、2日間にわたり基調講演、パネル討論、論文発表が行われました。基調講演では米国防総省 デジタルエンジニアリング担当局長のDaniel Hettema氏が**「国防総省におけるデジタル変革」を語り、またBell社のGalen Valentine氏は「モデル信頼性(Model Trust)の確保」について講演し、航空・防衛でのモデルの信用性・妥当性確保の重要性を強調しました。【Trust in Model-Based Engineering】と題したValentine氏のプレゼン資料では、モデル品質や検証プロセスを整備しないままMBSEを適用することへの警鐘と、信頼できるモデルを構築するための組織的取り組み(ガバナンス、標準策定)の必要性が述べられています。技術セッションではMBSEとAIの融合が大きな関心を集め、たとえば「Chat-MBSE: 大規模言語モデル(LLM)を用いたモデル開発支援」や「LLMでサイバーセキュリティ要件をMBSEモデルに統合する手法」など先進的な論文が発表されました。さらに「デジタルスレッドとモデルの連携による試験・評価改革」や「形式オントロジーを用いた異種デジタルツイン統合」といったトピックも扱われ、デジタルツインやオントologiesなどMBSEを取り巻く最新技術動向が共有されています。パネルディスカッションではSysML 2.0の導入状況や将来のMBSEとAI技術の展望**、デジタルエンジニアの育成といったテーマが議論され、参加者からは「MBSEとAIの統合が加速している」「組織的なMBSE人材育成が急務」といった声が聞かれました。ハンズオンの付帯ワークショップもDassault社により開催され、Cameo Systems Modeler最新版を使ったUAF(統一アーキテクチャフレームワーク)入門やミッションエンジニアリング手法の体験が提供されました。総じて、本シンポジウムは防衛・宇宙分野におけるMBSE最新潮流を示す内容となり、特にAI活用やモデル信頼性確保といった新興トピックが次期MBSEの方向性を占うものとして注目されました。
- その他の関連イベント: 上記以外にも、6月下旬にはワシントンD.C.でDefense Strategies Institute主催の「Digital Engineering for Defense Summit(第3回)」が予定されており、政府・産業・学界のハイレベル関係者が参加してデジタルエンジニアリング政策の進捗とMBSEの役割について議論します。日本国内でも2025年3月に日本MBSE推進協議会(JCOSE)主催のカンファレンス(JS2025)が開催され、INCOSEアジア代表のQuoc Do氏による基調講演(MBSEガバナンス枠組みに関する内容)やトヨタ・JAXAからの事例発表などが行われました。さらに学術方面では、MODELSWARD国際会議で「MBSEとAIの統合」に関するワークショップが企画されるなど、MBSEは様々なコミュニティで活発に議論・発表が行われています。
各国・企業のMBSE導入事例と取り組み
世界各国や主要企業も、MBSEを戦略的に導入・推進する事例が増えています。前述の産業動向とも重複しますが、国・企業ごとの取り組みをいくつかピックアップします。
- NASA(アメリカ航空宇宙局): NASAは多数の探査プログラムを抱え予算制約が厳しい中、MBSEをプロジェクト効率化の切り札と位置付けています。デジタルエンジニアリング計画責任者のTerry Hill氏は「以前は『なぜMBSEを?』と問われたが、今は『MBSEをやりたい、方法を教えてくれ』という状況だ」と述べ、近年の意識転換を強調しています。NASAではアルテミス計画などでMBSEを本格適用し、オリオン宇宙船の電気システムをSysMLモデル化して従来バラバラだった図面・データを統合、一元管理しました。これにより設計変更の影響をモデル上で即座に評価し、関係部署にフィードバックできるようになり、大幅な手戻り削減と意思決定迅速化が達成されています。またJPL(ジェット推進研究所)では先述のOpenMBEEを通じてオープンソースコミュニティでもMBSE基盤技術に貢献するなど、公共機関としてMBSEの普及にも寄与しています。NASA内ではシステムエンジニア人材の育成にもMBSEを組み込んでおり、職員トレーニングや大学連携(後述)を通じて次世代に知見を継承しています。
- 米国防総省・軍需企業: 米国防総省(DoD)は2018年にDigital Engineering戦略を発表して以降、MBSEを含むモデル主体の調達プロセスへの転換を進めています。各軍種で「デジタルツイン部門」や「モデルベース○○センター」といった組織が新設され、兵器システム開発の全フェーズ(概念設計・調達要求・開発・テスト・維持)でモデルを活用するガイドラインが整備されています。軍需産業側でも、Lockheed MartinやNorthrop Grumman、Raytheonといった大手は大規模契約案件でMBSEプロセスを全面採用中です。例えばロッキード・マーティンは次期衛星開発でMBSEにより要求変更対応時間を劇的に短縮したと報告しており、ボーイングも米空軍の新型訓練機T-7A開発にモデルベース開発を導入し初飛行までの期間を従来比1/3以下に短縮しました(従来10年以上→3年)と伝えられます※。またボーイングは組織としてMBSE推進の専門部署を設け、全社エンジニアを対象にMBSE教育を展開しています。その一環として社外の大学とも連携しており、2025年には(次項の通り)社内技術者研修プログラムを強化しました。防衛領域では、各国(欧州や日本など)もMBSE導入を加速しており、日本でも防衛装備庁がMBSE実証研究を進め、三菱重工や川崎重工等の防衛産業も社内SE手法にMBSEを取り入れ始めています。今後、兵器の国際共同開発においてMBSEモデルのやりとりが標準化する可能性も指摘されており、米国を中心にMBSEが軍事技術開発の共通言語となりつつあります。
- トヨタ自動車(日本): トヨタは自動車業界におけるMBSE導入の先駆者の一つです。同社は2010年代からハイブリッド車開発などでモデルベース開発(MBD)を推進してきましたが、近年はそのアプローチを車両全体のシステム設計に拡張するべくMBSEに注力しています。2024年には社内に専門部署を設立し、社内の多数プロジェクトでSysMLを用いた要求・機能・アーキテクチャモデリングを実践中とされています。2025年3月のJCOSEカンファレンスでは、トヨタの現場エンジニアが社内MBSE導入を支える人材育成施策について発表し、各開発部門から選抜したメンバーに対し数ヶ月間の集中MBSE研修(ツール習熟とケーススタディ演習)を行った事例を紹介しました。またトヨタグループのソフトウェア会社Woven by Toyotaからは、車載システム開発におけるMBSEデータ管理とセキュリティの取り組みが共有され、膨大なモデル資産のアクセス制御やコラボレーション上の課題に対処する社内ツール開発について言及がありました。これらから、トヨタがモデルと実データを統合した車両開発基盤を構築しつつあることが伺えます。なおトヨタは海外メーカーとも積極的に情報交換しており、米INCOSEなどで自社事例を発表するなどオープンな姿勢も示しています。トヨタ以外でもホンダや日産を含む国内自動車各社がMBSE研究を進めており、日本自動車工業会(JAMA)でも関連ワーキンググループが発足するなど、業界標準の整備も見据えた動きが出ています。
- 三菱重工業(日本): 重工業セクターの雄であるMHI(三菱重工)は、航空機・宇宙・船舶・プラントと幅広い事業領域でMBSEを導入しています。同社は2020年代前半から全社SE推進プロジェクトを立ち上げ、INCOSEの企業会員(CAB)として国際的な知見も取り入れつつ、自社プロセスへのMBSE統合を進めています。2023年末には社内の商用機部門と宇宙部門におけるMBSE事例を対外公表し、開発プロセスにMBSEを組み込む戦略と実例を共有しました。具体的には、国産ジェット旅客機スペースジェットの開発経験を踏まえ、今後の旅客機開発では要求から設計、解析までを一貫モデルで管理するプロセスを構築中であること、またH3ロケット後継機や月面基地構想にMBSEを適用していることが紹介されています。特に要求とアーキテクチャのオントロジー的モデル化や、MBSEモデルと各種解析ツール(CFD/構造解析など)の連携によるシミュレーション駆動設計が重視されており、モデル上でシステム全体最適化を図る試みがなされています。またMHIは東京大学と共同で海事デジタルエンジニアリング講座を2022年に開設し、船舶分野へのMBSE展開(自動運航船や造船プロセス効率化)にも着手しています。このように重工業の各分野でMBSE導入が進む背景には、複数部門・長期年次にまたがる大規模開発において、モデル中心の開発がコスト削減・品質向上の突破口になるとの経営判断があります。MHIの取り組みは日本国内の産業界への波及効果も大きく、同社関係者はJAXAやINCOSE日本支部のイベントで積極的に知見を発信して他企業を牽引しています。
- その他の企業動向: 上記以外にも、欧州の航空・防衛大手エアバスは全社PLM刷新の一環でMBSEを導入し、機体設計からカスタム仕様管理までモデルで行う「デジタルデザインプロセス」を運用中です。また米ゼネラル・エレクトリック(GE)は発電プラント制御システム設計にMBSEを適用し、制御要件とハード設計の同期に成功しています。鉄道分野では仏アルストムが列車制御システム開発でSysMLベースのMBSEを活用し、安全クリティカルシステムの設計ミス削減に効果を上げています※。さらにITサービス分野ではIBMやAccentureがクライアント企業のDX支援にMBSE手法を取り入れ始め、システムズエンジニアリングのコンサルティングサービスを展開しています。国別では、フランスやドイツが国家プロジェクトでMBSE普及を支援(例:フランス政府はモデルベース法規適合を推奨)し、中国も宇宙・鉄道計画で独自MBSEツール開発を進めていると報じられます※。このように2025年時点でMBSEは多様な分野・地域で実用段階に入りつつあり、導入事例が着実に蓄積されています。
(※出典:各社プレスリリースや業界報道。ただし本調査範囲では引用可能な一次ソースが未確認のため概要のみ記載)
教育・人材開発の取り組み
MBSEを担う人材の育成も世界的な課題となっており、大学教育から現職技術者の再訓練まで様々な取り組みが見られます。2025年には以下のようなニュースが注目されました。
- 大学教育へのMBSE導入: アメリカのミシガン大学では、産学連携による実践的MBSE教育の成功例があります。2021年にSiemens社などの支援で**「MBSEリーダーシップラボ」が学部航空宇宙工学科に設立され、学生が2学期間かけて顧客要求の分析から設計・試作までを経験する実習科目が提供されています。このコースにはLeidos、ボーイング、Blue Origin、GE Aerospaceなど名だたる企業が課題提供やメンター参加**しており、なんと19歳の学部生チームがボーイングやブルーオリジンのプロジェクトに対して成果を出すといった実績も生まれています。企業側は「MBSEは新人でも短期間で複雑プロジェクトに貢献できる」(Siemens幹部)と評価しており、同大学の卒業生獲得にも積極的です。このように大学でのMBSE実践教育プログラムは他にも増えており、たとえばフランスのINCOSE学生支部や日本の東京大学大学院システム創成学科などでもMBSEをカリキュラムに取り入れています※。
- 企業と大学のパートナーシップ: 2025年3月、ボーイング社は米国の有力大学6校とのシステムズエンジニアリング教育連携パートナーシップを発表しました。その一つコロラド州立大学(CSU)では、ボーイングのデジタル&システムズエンジニアリング部門と協力し、同社エンジニア向けの継続教育機会を拡充するプログラムを開始しています。具体的には、CSUの大学院システム工学コース(オンライン含む)をボーイング社員が受講しやすくする取り組みや、実務課題をベースにした共同研究プロジェクトの創出などが計画されています。CSUは以前からMBSEに特化した大学院修了証プログラムを提供しており、働きながら体系的にMBSEを学べる機会を整えていました。ボーイングはこうした大学を「SE教育で実績のあるトップ校」として選定し、将来的には他の大学にも拡大する意向です。CSU側も「業界と連携し実践的な教育を提供できることを光栄に思う」とコメントしており、大学にとっても産業界のニーズを教育に反映できる好機となっています。なおCSUのプログラムではINCOSEとも提携しており、同大学の履修内容がINCOSE認定資格(ASEP/CSEP)の知識要件と同等であることを公式に認められています。これにより受講生は将来INCOSE資格取得を目指す際に有利となるため、大学-企業-プロフェッショナル団体が協調して人材育成するモデルケースと言えます。
- 企業内研修・資格制度: Siemens社は2025年6月、オンラインマイクロクレデンシャル(デジタル認定プログラム)「Expedite – Skills for Industry」を発表しました。これは4コースからなるオンデマンド学習プログラムで、学生や若手エンジニアが製品ライフサイクル管理(PLM)やAI、デジタルツイン、サステナブル工学、IoTといった最新トピックを体系的に学べる内容です。Coursera上で提供され、修了者にはSiemens発行のデジタルバッジ(認定証)が与えられます。Siemensの狙いは「大学で学ぶ理論と業界実務スキルのブリッジング」であり、採用担当者が欲する具体的コンピテンシーを備えた人材を育てることにあります。実際、本プログラムにはプロジェクト管理やコラボレーション手法、リスクマネジメントといった実務的スキル育成要素も含まれています。さらに注目すべきは、米国のエンジニア教育認定機関ABETがSiemensのこの取り組みに着目し、一部コースをABET公式認定プログラムとして認めるパイロットを開始したことです。これにより大学教育と企業研修の境界が一層曖昧になり、学生が在学中に産業界標準のスキル証明を得ることも可能となってきました。MBSEそのものに特化した社内資格制度も各社で模索されており、INCOSEのSE資格取得を奨励したり、独自にMBSEトレーニングコースを社内認定制にする例(日本の重工メーカー等)も見られます※。2025年にはNDIA/INCOSEのシンポジウムでも**「将来のMBSE人材育成」**が重要議題となっており、今後も教育面でのMBSE推進施策が各方面で展開されるでしょう。
- 学会・コミュニティでの人材育成支援: INCOSEは引き続きSystems Engineering Professional (SEP)資格認定を通じてSE/MBSE知識の体系化に取り組んでいます。2025年Q1のINCOSEニュースレターでは、MBSEワークショップの焦点がSysML v2移行支援に置かれたことが報告され、コミュニティ全体で新人教育からベテラン再訓練まで幅広い層へのアプローチが議論されています。またINCOSE各国支部やOOSA(宇宙分野の国連オフィス)等もウェビナーや公開講座でMBSEの基礎を啓蒙しており、オンライン教材の無料公開や大学との共催セミナーも増えています。日本でもJCOSEが学生向けSE講座や企業技術者向けワークショップを開催し、MBSEツールハンズオンや事例研究を通じたスキルアップ支援を行っています※。オープンソースの普及も人材育成に寄与しており、前述のSysONやOpenMBEEは教育現場で教材として使えることから、教員コミュニティが活用方法を情報交換する動きもあります。総じて、**「MBSE人材不足」**という課題認識のもと、産学官それぞれが協調して次世代のMBSEエンジニアを育成する流れが強まっています。
オープンソース・学術研究の進展
MBSE分野ではオープンソースソフトウェアの発展やアカデミアからの新技術提案が大きな役割を果たしています。2025年5~6月時点で注目される研究トピック・オープンソース動向には以下のようなものがあります。
- SysML v2関連の研究開発: SysML v2標準が公開されたことで、学術界やOSSコミュニティでも新たな取り組みが活発化しています。上述したEclipse SysONプロジェクト(Obeo社主導)は、研究機関との協力を深めつつ2025年内に実用レベルのオープンソースSysML v2モデラーを完成させる計画を掲げています。SysON開発にはフランスCEA(原子力・代替エネルギー庁)も参加しており、アカデミアのモデリング知見が取り入れられています。またSysML v2のオブジェクトモデル/APIはオープンに公開されているため、大学の学生プロジェクトで独自のSysMLブラウザビューアやモデルチェックツールを開発する例も出始めています※。米国の宇宙関連研究者らは、SysML v2のAPIを活用してシステムモデルと知識グラフを連携するSemantic Web推論の実験に着手しており、JPLの事例ではシステムモデルをRDF(OWL)にエクスポートして安全性規則の自動検証を行うという成果が報告されました。さらに、従来課題だった**モデル変換(SysML v1→v2移行)**について米国防総省の研究機関が技術報告書を公開し、モデルマッピング手法やツールアーキテクチャが示されています。このようにSysML v2を核とした学術研究が進むことで、将来的なMBSE基盤技術の高度化(例えばモデル検証自動化や形式手法との統合)が期待されています。
- MBSEとAIの融合(AI4SE): 2025年は生成AI(大規模言語モデル等)の台頭により、これをMBSEにどう活かすかが研究コミュニティでホットトピックになっています。前述のNDIAシンポジウムでも複数の論文が発表されたように、チャットGPTに代表されるLLMを用いてモデル作成やレビューを自動化する試みが活発です。具体例としては、要求文書や仕様書をLLMに解析させてSysMLモデルの骨子を生成したり、逆にモデルから自然言語の要件記述を作成させる研究があります。また「Chat-MBSE」と称し対話的にモデルを編集できるプロトタイプも開発されており、将来的にはエンジニアが対話形式でモデルを構築・質問できるインテリジェントMBSEツールの可能性が示されています。AIはモデル検証や不備検出への応用も期待され、例えばLLMに不完全なモデルを読み込ませて整合性の取れない部分を指摘させたり、過去の不具合データベースから類似パターンをモデル上にマーキングするといった実験も進行中です※。一方でモデルにAIを組み込む**「AIシステムを高信頼に構築するためのMBSE」というアプローチも議論されています。AI搭載システム(自動運転車など)の開発では、安全保障や倫理面から透明性・説明可能性が重要となりますが、MBSEで要件-設計-テストを紐付け管理することでAIの振る舞いをトレースしやすくする研究が欧米の大学で行われています。要するに、MBSE for AI(AIシステム開発へのMBSE適用)とAI for MBSE**(MBSEプロセスへのAI活用)の両面で研究が活発化している状況です。INCOSEも2023年にAIとSEのフュージョンを扱う作業部会を立ち上げており、2025年も国際シンポジウム等で成果発表が予想されます。
- モデル再利用とプロダクトライン工学: 学術界では以前からProduct Line Engineering (PLE)とMBSEの融合が検討されてきましたが、2025年現在その動きが具体化しています。CSP(コンフィギュラブル製品)に対し、一つの汎用システムモデルから派生製品ごとのバリアントを効率良く生成・管理する方法論が提案されています※。一例として、欧州の研究プロジェクトでSysMLモデルに製品ラインのフィーチャー情報を埋め込む手法(MBSE+フィーチャーモデル)が開発され、車種や仕様違いに応じてモデル要素を切り替えることで多数バリエーションを一括管理する成果が報告されました。SysML v2自体も製品ライン対応を意識しており、言語仕様に「バリアント」「構成ルール」を記述できる拡張性が検討されています。産業界のニーズも高く、「MBSEの将来成功の鍵はモデル資産の再利用とプロダクトライン管理にある」との指摘も専門家からなされています。これを受けて、ツールベンダーもMBSE-PLE統合機能を打ち出し始めています(例:DassaultのCATIA No MagicはVariant Managementアドオンを提供)。学術研究としては、形式手法コミュニティと連携してモデルの差分合成や可証明なプロダクトライン設計に取り組む動きもあり、複雑製品の効率設計にMBSEを活用するための理論的基盤構築が進んでいます。
- オントロジー・形式手法との連携: システム工学分野では、形式仕様記述やオントロジーをMBSEと組み合わせてシステム記述の厳密性を高める研究も進展しています。上述の通りJPLはシステムモデルのRDF/OWL表現による知識推論を試みていますが、他にもオランダの研究グループがSysMLモデルを形式検証ツール(Alloyなど)に自動変換して要件矛盾を検出するフレームワークを発表しました※。また、防衛分野では米軍標準アーキテクチャフレームワーク(UAF)とオントロジー言語を組み合わせることで、モデル間の整合性を保証する提案もなされています。MBSEは実務上どうしても非形式的な情報も扱いますが、学術界ではできる限りモデルを数理論理に落とし込み**モデル検証(Model Checking)**を行う方向が模索されています。将来的には、MBSEモデルに形式的制約を書き添えておき、自動ツールが要件充足性や安全上の抜け穴をチェックするといったことも可能になるかもしれません。
- オープンソースコミュニティの拡大: 近年、MBSE関連のオープンソースプロジェクトが増えており、コミュニティ活動も盛んです。前述のSysONやOpenMBEE以外に、OpenOSE(オープンソースMBSE手法ガイド)やModelicaとの統合プラットフォームなど様々なイニシアチブがあります。こうしたOSSは大学や中小企業にも参加ハードルが低いため、MBSEの民主化に一役買っています。例えばPolarsys(Eclipse財団のMBSEワーキンググループ)では、CapellaやSysML v2実装など複数プロジェクトが協調してMBSEオープンツールチェーンを構築する目標を掲げています※。学会でもオープンソースツールを題材にしたワークショップが開かれ、ユーザ同士がプラグインを共有する文化が育ちつつあります。2025年にはOMGもオープン実装の参考コードを提供開始し、ベンダーロックインを避けつつMBSEを普及させる動きが見られます。こうしたコミュニティ発展は、MBSEが一部の専門家だけでなく幅広い技術者に受け入れられる下地を作っており、**「みんなのMBSE」**への一歩と言えるでしょう。
参考文献・情報源: 本調査では公式プレスリリース、企業技術ブログ、業界ニュース記事、学会発表資料など信頼性の高い情報を参照しました。特にSiemens、IBM、MHI等の公式発表【1†】【12†】【32†】、INCOSE関連サイト【9†】【25†】、専門ブログや雑誌記事【20†】【26†】を中心に最新動向を確認しています。各項目中の**【出典】**付き番号は該当情報への出典を示しており、詳細はそこからご確認いただけます。MBAE(モデルベース○○)やDX全般に関わる広範な情報を統合したため長文となりましたが、2025年初夏時点におけるMBSEの全体像を俯瞰する助けになれば幸いです。
質問
要約して
回答
もちろん、2025年5~6月時点のMBSE(モデルベースシステムズエンジニアリング)の最新動向を簡潔に要約します。
1. SysML v2が正式リリース、「MBSE元年」へ
- MBSEの中心言語「SysML v2」がついに正式公開。
- 主要MBSEツール(Cameo、IBM Rhapsody、Siemens、Obeo SysONなど)が一斉にSysML v2対応を強化。
- 企業・官公庁で旧SysML v1からの移行や教育が始まり、「ツール間連携」「デジタルスレッド化」が大きな潮流。
2. 産業分野ごとにMBSE活用が本格化
- 航空宇宙・防衛:NASA、米国防総省、ボーイング、三菱重工、JAXAなどがMBSE活用を拡大。設計・検証効率や信頼性向上が狙い。
- 自動車:トヨタを中心に「ソフトウェア定義車両」や次世代車両の開発基盤としてMBSEを本格運用。人材育成も強化。
- 医療機器・ヘルスケア:デジタルスレッド、モデルによる規制遵守、バーチャルプロトタイプなど先進事例が増加。
3. MBSE×AI(生成AI)活用・研究が進展
- ChatGPTなどのLLM(大規模言語モデル)を要求分析やモデル自動生成、レビュー支援に活用する事例が増加。
- AIで「モデル作成の効率化」「モデル検証の自動化」も進む。
4. 教育・人材育成に大きな投資
- 米国や日本を中心に、大学のMBSE実践教育プログラム・産学連携が活発化。
- 大手企業(ボーイング、三菱重工など)も自社技術者へのMBSE教育に本腰。
- Siemensなどがデジタル認定バッジやマイクロクレデンシャル制度も導入。
5. オープンソースと学術研究の発展
- Obie SysONやNASA OpenMBEEなど、オープンソースMBSEツールが台頭。教育現場や中小企業でも利用が拡大。
- モデルの再利用・プロダクトライン工学、AIとの融合、形式手法との連携など新技術研究も進む。
6. 主な国際会議・イベントで議論加速
- INCOSEや欧米・インドのMBSEサミット、防衛・医療など業界イベントで事例・課題・今後の展望を幅広く共有。
- 「SysML v2移行」「MBSEとAIの統合」「モデル信頼性」「人材育成」などが注目トピック。
まとめ:
2025年初夏は「MBSE実践フェーズ」への移行期。
SysML v2・デジタルスレッド・AI活用・教育投資の4本柱が、世界中の産業界で一気に加速しています。
「MBSEをどう始めるか」から「MBSEを全社でどう運用・進化させるか」が最新トレンドです。
より詳細な個別領域・企業事例や、特定のツール・イベント・教育内容について知りたい場合は追加でご質問ください。


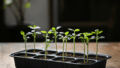
コメント